前回は鉄骨の工作図のチェックポイントの1~4をお伝えしました。
今回は続きをお伝えします。
5.各部の取合い部分の納まり
柱と梁がどの様に接合しているのか?
柱の足元はどの様な納まりか?(ベースプレート部)
などは、
通常時のみならず、地震時などに負荷がかかってくる所なので、
万が一部材が破断などしてしまうと、建物全体に影響を及ぼす
可能性が高いので、じっかりと確認しておくべき箇所です。
特にダイアフラムとかベースプレートなどは、厚みや素材が
特記仕様書や詳細図にだけ記載されていたりする場合も
あるかもしれないので構造図の隅々まで一度確認してから
図面チェックをした方が良いですね。
6.接合部(スプライスプレート等)に関する設計図書との照合
鉄骨部材同士はほとんどの場合、ボルトや溶接でつなげていきます。
なので、接合部の仕様を間違えてしまうと、地震時などで期待していた
耐力がもたない可能性が有ります。
だから
- 高カボルトの種類・径・本数・ゲージ・ボルト間隔・最小縁端距離等
- 溶接の種類・開先形状・大きさと寸法・長さ・位置等
- アンカーボルトの種類・径・長さ・本数・位置等
- SRC 造の場合の鉄筋工事との関係
については、構造図の通りか?をよく確認しておいて下さいね。
また
梁がピン接合の場合で、柱や梁から出たガセットプレートに
梁を取り付ける場合は、梁の芯は鉄骨芯と同じですが
梁を鉄骨芯に取り付けるためには、ガセットプレートを
梁のウェブ厚さの半分、ずらして取付なくてはいけないですが、
ずらす方向と、実際の施工時の方向があっていなければ、
鉄骨梁が本来の位置とズレた位置になってしまいます。

他には
四角い形状の建物であれば、あまり当てはまらないかも
知れませんが、変形している建物であれば、
「このボルト、どうやって締めるの?」
という箇所があるかもしれません。
この件は、また後日お伝えしますね。
頭の中で実際に、組立てる所を想像しながら図面をチェック
できるか?が意外とカギになることもありますよ。
7.他の建築工事(内装工事等)との関連
鉄骨は建物の根幹をなす構造ではありますが、
躯体だけを考えておいて良いわけではありません。
以前、コンクリートの時にも言った気がしますが
建物の完成形から、だんだん仕上を取っていって
残ったのが躯体なので、当然ながら仕上の事も
考えながら鉄骨図をチェックしなければいけません。
例えば
建具のフロアヒンジなどの床埋め込みの金物が鉄骨に
当たってしまって納まらない。という場合は、鉄骨を切ればよい。
ということにならないので、もうどうにもなりません。
また
鉄骨にALCなどの壁や、建具がとりつく場合などは、
取付位置に予めピースを仕込んでおくなどの処置も
必要になるので、仕上関係の担当者と打合せを行って
手戻りの内容に進めて下さいね。
「鉄骨に直接あとから溶接すれば良いや」
と簡単に考えていると、溶接長が足らなかったり
品質上問題のある取付方法になる可能性が高いです。
長くなったので続きはまた次回。

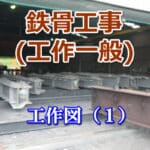






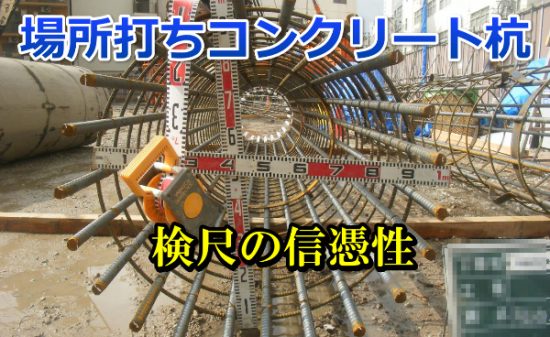


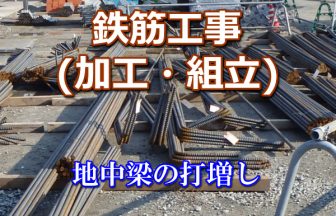


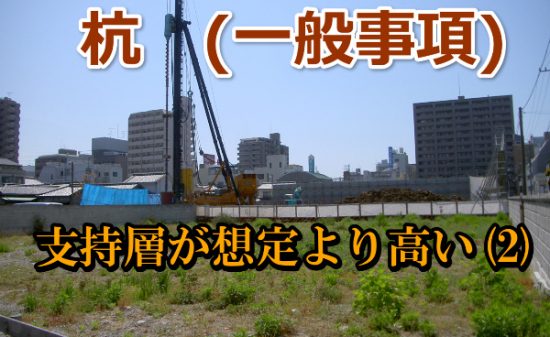










































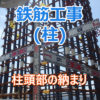
この記事へのコメントはありません。