骨材で一級建築士の試験に出てくる内容は、「粗骨材の最大寸法」が一般的で、
コンクリートの配合の基準値として登場するか?鉄筋のあき寸法を
決める基準の1つとしても登場します。
そして
粗骨材の最大寸法が基準値として採用されているか?というと、
勘の良いあなたなら分かっていると感じますが、
コンクリート打設中に粗骨材が鉄筋に引っ掛かって、
コンクリートの充填に悪影響を与えて、型枠を脱型したら
「あちゃ~~っ」という事を減らす為なのです。
更に
粗骨材と細骨材の比率として「細骨材率」についても、
試験には出てきませんが、配合報告書のなかで確認される項目です。
しかし
今回のテーマは一級建築士の試験にも配合報告書にも記載されない事です。
私は今まで東北で仕事をしたことはないのですが、ある人に
「仙台のコンクリートの粗骨材は川砂利みたいに丸いんだよね」
と言われた事があります。でも、私の中の粗骨材はゴツゴツしていて
角が尖っているものというイメージですが、あなたはどんなイメージですか?
そうです!今回のテーマは
「骨材の形はどんなものでも良いの?」
なのです。一級建築士の試験にも、配合報告書にも粗骨材の種類が
出てきたとしても形状まで書いてないし、形状に対する優劣も
記載されていません。文句を言っても地域性があるので難しいのです。
でも
実際のコンクリートの性能について「粗骨材の形状」が
意外も大きな影響を与えていると言うことは知っておいて損はありません。
現実的には、粗骨材は粒の大きさがほぼ揃っていて、
角がない球形に近い形状の方が品質の良いコンクリートが
製造しやすい事が分かっていますが、完全に夢物語なのです。
実は
次回あたりにお伝えしようと考えていますが、
粗骨材のほとんどは石などを砕いた「砕石」なので
角のあるゴツゴツした形状なのですからね。
最後に
「建築工事監理指針(令和7年版上巻)」
の該当部分を確認して下さい。
P.380
(カ) 粗骨材の最大寸法等
(a) 粗骨材の最大寸法
粗骨材は、鉄筋相互間及び鉄筋とせき板 との間を容易に通る大きさでなければならない。粗骨材の最大寸法は「標仕」において次のように定めている。① 砕石、高炉スラグ粗骨材、電気炉酸化スラグ粗骨材及び再生粗骨材Hは20mmとする。 また、砂利は25mmとする。
② 基礎等で断面が大きく鉄筋量の比較的少ない部材の場合は、「標仕」5.3.5[鉄筋のかぶり厚さ及び間隔]の範囲で、砕石、高炉スラグ粗骨材及び再生粗骨材Hは25mm、また、砂利は40mmとすることができる。
③ 鉄筋のあきは、粗骨材の最大寸法の1.25倍以上とする(「標仕」5.3.5 (4)(ア)参照)。
④ 無筋コンクリートの粗骨材の最大寸法は、コンクリート断面の最小寸法の1/4以下とする。ただし、捨コンクリート及び、防水層の保護コンクリートの場合は25mm以下とする(「標仕」6.14.2 (1)参照)。
(b) 骨材の粒度及び粒形
① 骨材は、適切な粒度分布のものでなければならない。粒度の良否によってコンクリートのワーカビリティーや単位セメント量に著しい差が生じ、ひいてはコンクリートの強度や耐久性にも影響を与える。
② 骨材の形は、球形に近いものが理想的で、偏平、細長のもの、かど立っているものなどは、コンクリートのワーカピリティーを悪くし、同一水セメント比で同一スランプを得るための細骨材率が大きくなり、単位水量、単位セメン卜量も多くなる。また、偏平、細長のものは、コンクリートが外力を受けたときに不均ーな応力分布が生じて、破壊しやすいためにコンクリー卜の強度も低下する。
③ 粒度分布を表すには次のような方法があり、通常1)及び2)が用いられる。
1) 各ふるいの通過率
2) 組粒率(FM)
3) 各ふるいの累加残留率
4) 各ふるいの残留率④ コンクリートの品質を確保して圧送性を良くするには、骨材の粒度分布が適切であるとともに0.3mm以下の細骨材が15~30%混入していることが望ましい。
つまり
コンクリートの粗骨材で最大寸法の以外で品質に影響を与えるものは
粒度分布が均一な粗骨材に比べ偏平であったり角が立っている
粗骨材などはコンクリートのワーカビリティーが悪くなるので
水セメント比を上げるために細骨材率や単位セメント量、単位水量
が増加してしまうため、強度やコストパフォーマンスが悪くなります。
また
粗骨材の最大寸法については、コンクリート内の「鉄筋のあき寸法」に
影響を及ぼすように、型枠内のコンクリートの充填性を確保するために
決められていますが、建築で使用するコンクリートの99%は20mmです。
ここで
「鉄筋のあき寸法」が出てきましたが、あき寸法の基準が
「コンクリートの粗骨材の最大寸法の1.25倍」について
「1.25倍」の意味って知っていますか?
こちらの記事で答え合わせをしておいて下さいね。
↓ ↓ ↓
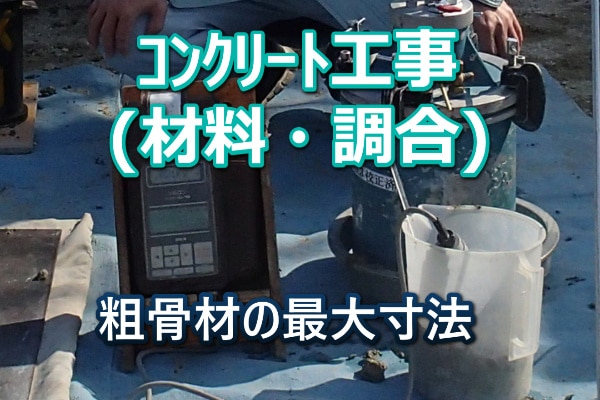

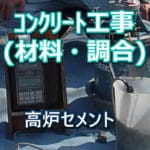
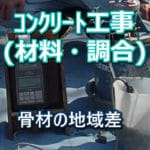





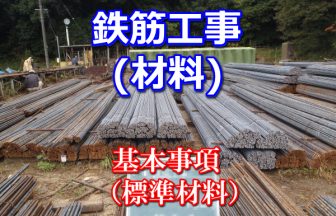






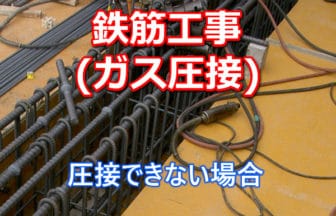






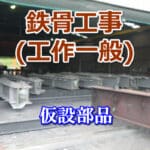







































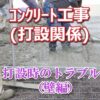



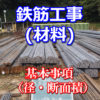

この記事へのコメントはありません。