[mathjax]
前回の記事から、大分時間が経ってしまいました。
足場の風荷重の算定方法とは?(1)
足場の風荷重の算定方法とは?(2)
こういう構造計算系の記事は資料を見ながら書かなければならないので
最近、通勤時間に記事の下書きをしたり、お問い合わせの返信をしている
私のライフスタイルからすると腰が重くなってしまうのです。
だから
今回はずっと喉につかえていた続きから書いていきます。
前回までで荷重を設定する部分は終わり。
今回からは、実際に耐えることが出来るかどうかの判定です。
壁つなぎの許容耐力\((F_{k})\)
まずは
風荷重の検討は最終的にどこがゴールか?
という点だけど、風荷重を負担しているのは「壁つなぎ」である。
つまり、壁つなぎが風荷重に耐えることが出来ればOKなのだ。
そこで
壁つなぎの耐えられる力(許容耐力)についてお伝えすると
許容引張力・許容圧縮力ともに\(4410(N)\)である。
そして、壁荷重に作業する応力は主として風荷重によるので
なんと壁つなぎの許容耐力\((F_{k})\)は30%割り増すことが出来る。
よって
$$ F_{k} = 4410 \times 1.3 = 5733 (N) $$
となる。
一般部分の壁つなぎの検討
前回の記事で風圧力\(P(N/mm^{2})\)を算出をして、
壁つなぎの1本当たりの許容耐力\((F_{k})\)が出た所で、
次に必要になるのは負担する面積\((A)\)である。
風圧力\(P(N/mm^{2})\)と負担する面積\((A)\)の積が
許容耐力\((F_{k})\)以下であれば、壁つなぎの検討はオシマイ。
そこで
負担面積の考え方だけど、一般的に風の強さにもよるが
足場に対して1スパン置き、若しくは毎スパンで壁つなぎを取る。
1スパンおきであれば\(1.8(m) \times 2 = 3.6(m)\)の幅で計算することが多い。
そして
高さ方向は、よほど階高が高くないかぎり「階高ピッチ」が多い。
RC造の場合は1階ごとに打設していくので階ごとに壁つなぎを
設置する必要が有るので理解はしやすいだろう。
イメージはこんな感じ。
ここで
負担面積が確定したら、前回の記事の「その他の部分」の方の
風荷重を使用して
$$ p_{2} \times A < F_{k} $$
であればOKである。
もしも
NGとなってしまった場合は、負担面積を変化させることによって
対応するようにしようね。めちゃめちゃ風の強い地域であれば
ビックリするほど細かく壁つなぎを設置しなければイケないかも。
という所で、壁つなぎの検討は9割は完了。
えっ?
「上層2層分の風荷重はどこに行ったか?」
それは、残りの1割だけど、長くなるかもしれないので次回に。
そこまで待てないあなたはこちらを手に入れて確認しよう。
↓ ↓ ↓
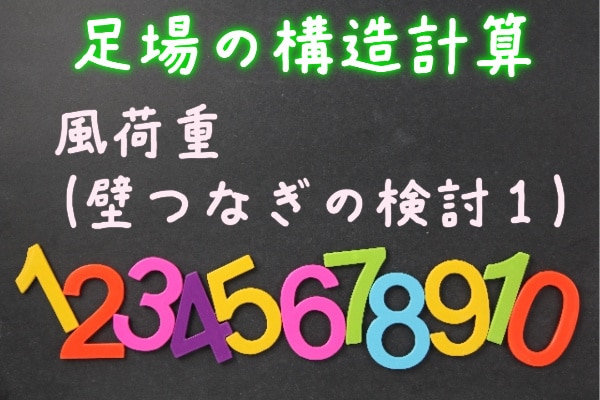



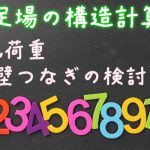




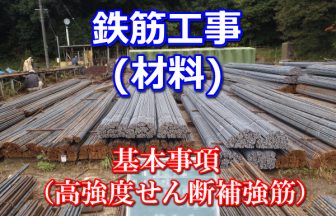

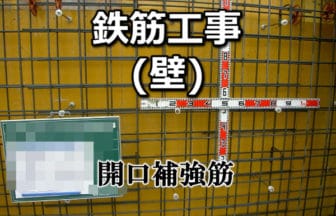
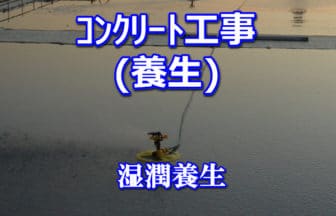

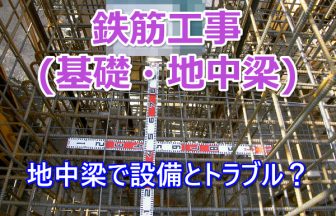
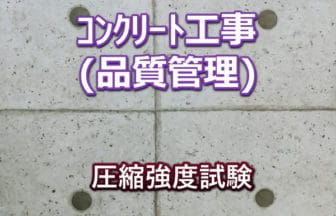

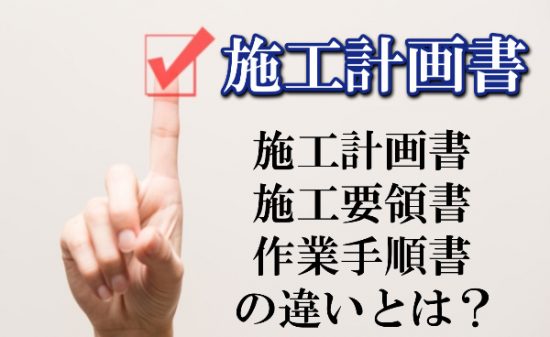





































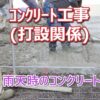




この記事へのコメントはありません。