鉄筋の接手においては、ガス圧接でも、機械式継手でも
溶接継手においても全数の外観検査が課せられています。
もちろん、溶接継手においても外観で分かるような欠陥があれば
結果として超音波探傷検査や引張試験を行っても欠陥が出る
可能性は非常に高いでしょう。
では
鉄筋の溶接継手の場合は、一体何の項目について
外観検査を行うべきで、重要な管理値は何なのでしょうか?
まずは
「建築工事監理指針(令和7年版上巻)」
の該当部分を確認して下さい。
P.355
(ア) 外観試験
(a) 外観試験は、全数の継手を対象とする。
(b) 試験項目及び合否判定基準は、表 5.6.2に よる。検査項 目の溶込み不良とは、裏当て材が残らない溶接工法の初層部において、溶込みが十分でなく開先面が残っている状態を言う。また、溶落ちとは、裏当て材が残る溶接工法において、裏当て材を適切な位置に取 り付けることができず、片寄って取り付けたことにより、裏当て材の隙間から溶接金属が流出する場合や、鉄筋径の異なる溶接継手において、裏当て材の密着度が悪く、裏当て材の隙間から溶接金属が異常に流出する場合をいう。
表5.6.2 溶接継手の外観試験項目及び合否判定基準 外観検査項目 合否判定基準 溶接の割れ 生じていないこと 溶込み不良 溶落ち ピット 直径が0.5mm以下 ビードの不整 隣接するビード表面の凹凸が2.5mm以下
ビード幅の最大と最小の差が5.0mm以下クレータのへこみ 周辺との差が1.0mm以下 余盛高さ 0を超え0.2d以下 アンダーカット 0.5mm以下 偏心 0.1d以下 折れ曲がり角度 3°以下 備考 d:母材の鉄筋径。異径継手の場合は細い方の鉄筋径
ここで
上記の表を確認して頂けると、外観検査で何を確認すれば良いか?
については大体お分かり頂けたのではないでしょうか。
ガス圧接に比べてノギスなどで測定する項目も少なくて、
溶接面が鉄筋より厚みがあり、表面上にクレーターなどの
欠陥がなければ「外観検査は合格」ということで比較的に
確認がしやすいのではないかとは思ってます。
ということで今回はお終りです。とすると、
私が一番伝えたいことは伝わっていません。
実は
今回の溶接継手の記事のどこかにも記載したのですが、
溶接継手の品質は「初層部」が一番大切です。
「初層部」というのは、溶接するはじめの個所でちょうど
裏当て金との接点となる部分で溶接する方向から見ると
「裏側」にあたる部分に欠陥ができやすいと言われています。
だから
私は先程「溶接継手の外観検査は道具を用いなくても可能」
とお伝えしたのですが、1つだけ現場に持って歩いて欲しい
道具が1つだけあります。
それは
|
|
で、この「点検鏡」を利用すると、スラブ上や梁上に立った状況で
裏側の溶接状況がお手軽に確認できるので非常にオススメです。
なぜなら
職人さんも資格を所有している「プロ」なので、溶接後に視界に入る部分に
不具合を残したまま作業を終えることはまず有りません。「あれっ」と
感じたのであれば、ちょちょっと修正して綺麗に仕上げるでしょう。
しかし
溶接の裏側については後から修正することが困難なので、
「実際に検査で確認する価値」が高いと私は考えています。
ただし
こちらの方法は全ての方法で適用できるわけではありません。
私が過去に経験した事のある工法は、CB工法とニューNT工法です。
CB工法であれば裏当て金がセラミックで施工後に取り除くので
初層部の目視による確認が出来ます。
しかし、ニューNT工法の裏手金は金属であり、施工後もそのままなので
永遠に初層部の目視確認は出来ませんので素直にあきらめましょう。
超音波探傷試験で溶接欠陥を見つけてもらうしかないですね。
つまり
溶接継手の外観検査で一番見るべきポイントは実は
「溶接部の初層側」なのです。
しかし
溶接継手の工法などでは一番大切な初層部の状態が
裏当て金によってみることが出来ない工法もあるけど
裏当て金がセラミックで出来ていて施工後に取り除く
CB工法などでは必ず確認しておきましょう。
それが
外観検査を結果的に楽にさせる方法につながるのです。
「えっ、なんで?」と感じたあなたはこちらの記事を
ぜひ読んでみて下さいね。
↓ ↓ ↓











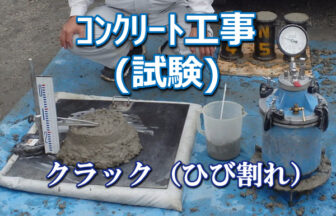






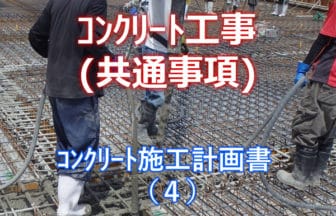





































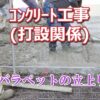




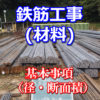
この記事へのコメントはありません。