前回は、型枠支保工用の足場の足元がコンクリートを打設したら
下がってしまったという話をした。
今回は、直接私が計画したわけでは無いけど先輩の計画を見て
「失敗じゃない?」と感じた話をしよう。
ここで、あなたに質問
「あなたは支保工足場の検討って自分で出来るかな?」
もしも、出来ると答える事が出来たなら素晴らしいと感じるよ。
そして
出来ないあなたは「誰に検討を頼む?」
社内の部署か、専門の業者に頼むか?
鳶や型枠大工などの協力業者に頼むか?
だけど、その時の先輩は自分で計算できなかったから
型枠大工に頼んだんだそのままの計画で工事を始めたのだ。
私は当時新入社員くらいだったので計画通りの図面で施工を進めた。
そして
出来上がった足場は、梁底を大引受に流した鋼管で直に受けるような
形状になっていた。が、別にその構造自体に問題があるわけでは無い。
確かに、型枠大工の支保工を組み立てる手間は1番掛からないように
計画をしているな。
とは、後々思ったけれど型枠大工に計画を依頼したから仕方ない。
では
どこが失敗なのか?
それは
梁の向こう側に行きたい時に非常に通行しにくいのだ。
具体的には
スラブ部分にはスラブ底から1700mm程度下がった所に床があるから
通行には全く支障は無いけど、梁を越える時は600ピッチに組んだ支保工足場を
かいくぐって向こう側に行くか?1度階段で下まで降りる必要があったのだ。
まだ、監督ならたとえ遠回りでも安全な通路を探して通行しようとするが、
作業員さんは同じようにはいかないよね。
アクロバティックに筋交いをすり抜けて移動していたけど、とても下に1度降りろ!
とは言えない状況であった事は確かだった。
それ以来
私が支保工足場を計画する場合はスラブ下1700mm程度の高さに、
フラットになるように梁の支保工足場も、スラブ下の棚足場も組み立てて
短めのパイプサポートで梁底をつく計画にしたのである。
すると、昇降階段も1箇所で済むし何よりも「非常に歩きやすい」
やっぱり、作業しやすい環境を作るとみんなが喜んでくれる。
実は
1番喜んでくれたのは「型枠の解体工」だったよ。
材料をその場で足場上から下に降ろして水平移動するよりは、
水平移動してからまとめて搬出する方が非常に効率的なんだって。
つまり
私の経験した事のある型枠支保工用の足場の失敗例とは
支保工を組み立てた後の人間の行き来の動線を考慮してなかったこと。
支保工用の足場としては、しっかりとした構造にはなっていたが
非常に使いづらくて苦情の嵐だったことを覚えている。
でも
「失敗は成功のもと」だし、「人の振り見て我が振り直せ」だと
私はいつも考えるようにしているよ。
大切なのは失敗した後のリカバリーだよね。
だから、こちらの記事も合わせて読んでみてね。
↓ ↓ ↓











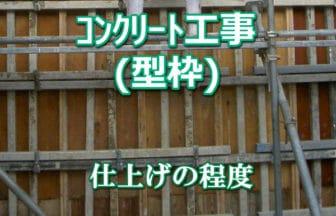




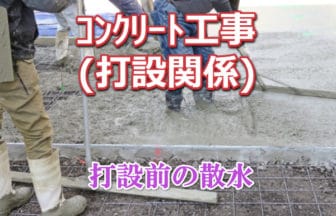












































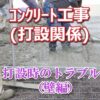
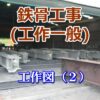
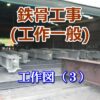
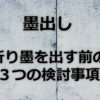
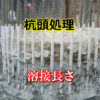
この記事へのコメントはありません。