鉄骨や鉄筋などの鋼材の品質証明は規格品証明書(ミルシート)で
管理するのが一般的で、ある程度の規模があれば現場毎に発注します。
すると
規格品証明書(ミルシート)には「現場名」が記載されているので、
あなたの現場の為に納入した材料だと言うことが一目瞭然となります。
柱や梁などの材料は必要長さを見越して出来るだけ材料ロスが出ないように
計算して使用すると残りはスクラップになります。
しかし
プレートなどの様な材料であれば、規格寸法のうち、使用する箇所が限定的で
半分以上が「余り」になってしまう場合もあります。
また、少量の汎用的な材料はロール発注せずに、流通している材料を
購入して使用する場合もあります。
では
現場毎にロール発注されていない鋼材は、
一体どの様に品質を証明するのでしょうか?
まず
1番最初に鋼材メーカーから出荷された時には、誰宛なのかは別にして
規格品証明書(ミルシート)が発行されますから品質証明は可能です。
そこから、問屋さんの方で一部分だけA社に売りたい時は、ミルシートの
「この部分を使っています」という部位を明確にして証明していきます。
更に、流通する時は同じ様に部分的に品質証明を行うという方法です。
その部分的に品質証明を行う書類を「原品証明書」 と呼び、
市場に出回る商品の品質を証明しているのです。
この制度は、いわゆる「性善説」に基づいて行われていますが、
この方法以外で材料を入手しようとすると、毎回鋼材メーカーへ
ロール発注しなくてはならず、製作スケジュールにも大きな悪影響を
与えてしまうため、今日現在では一般的なやり方です。
将来的には
材料にタグが仕込まれていて「ピッ」とすると、材料の品質が流通履歴と
共に証明される時代がくると考えていますけどね。
最後に
「建築工事監理指針(令和7年版上巻)」の該当部分を確認して下さい。
P.496
7.1.2 基本要求品質
(1) 鉄骨工事で使用する鋼材は、建物の構造耐力上必要な材質並びに断面形状及び寸法が設計図書で指定される。
基本要求品質としては、指定された材料が正しく使用されていることを求めているので、材質や寸法等を含めて、これを証明できるようにしておく必要がある。
板材等を切断して鉄骨部材を製作する場合は、一般的に、鋼材は製造工場 (メーカー)又は商社等から切板工場 (シャーリングエ場)等に出荷され、ここで必要な断面形状に切断され、さらに、鉄骨製作工場 (ファブリケーター等)で加工・組立が行われる。この過程において、鋼材の大半を物件ごとにロール注文する場合には問題になることは少ないが、鋼材問屋 (特約店)を通して市中購入する場合には、鋼材は順次小口に細分され、多様なユーザー等にわたっていくことがある。この時、鋼材そのものと、その規格品証明書 (ミ ルシート)が対になって動いていないことがある。特に鋼材等を部品に切断した場合、その切断された部品とミルシートの対応ができていないことがある。こうした状況を回避しつつ鋼材の品質証明を行う方法の例として、日本建築学会「鉄骨工事技術指針・工場製作編」の3.5.1を 挙げることができる。具体的には、鋼材の規格品証明書は原本であることを原則としつつ、原本と現品との対応確認を行った者の署名捺印等が記された (裏書きされた)規格証明書の写しを原本相当規格品証明書とすることや、流通経路に対応した鋼材と証明書の具体的な流れの例などが示されている。
なお、SN材の識別については、7.2.1(2)(ケ)を 参照されたい。
つまり
鉄骨を加工した余りを再利用するときに品質をミルシートで管理できるのか?
については、鉄骨などの鋼材等を部品に切断した場合、その切断された部品と
ミルシートの対応ができていないことがあるので、切断する前の鋼材の
製品番号等とミルシートが一致していることを前提としリスト化して
「鉄骨工事使用鋼材等報告書」を鉄骨工場にて発行して管理する
と言うのが望ましい。
実際に
プレート等の加工品の場合は、どの部分をどの様に使ったか?
を添付してある場合は視覚的に理解しやすいですよ。
更に
「ミルシート」と言えばこちらの記事も書いているので合わせて読むと
理解がより深まりますよ。
↓ ↓ ↓


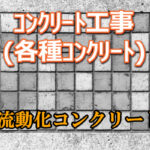





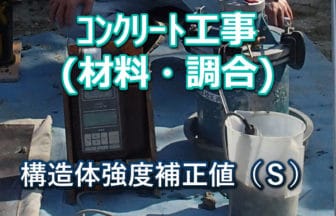


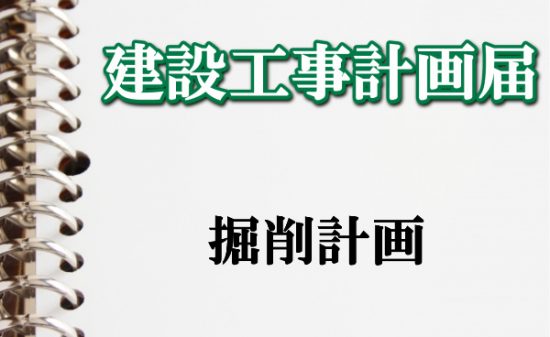
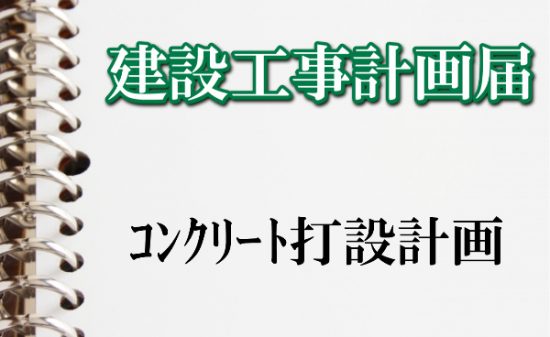
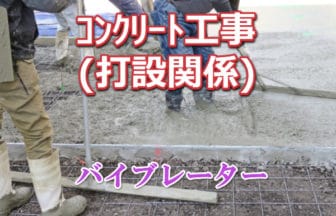

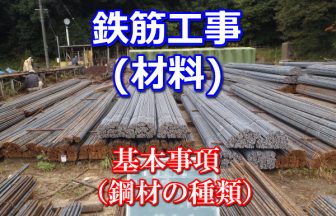
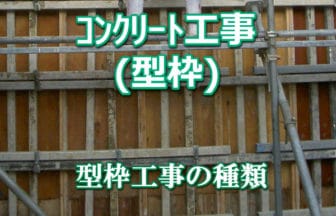









































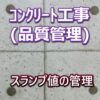


この記事へのコメントはありません。