「この部材図面ではSN材と書いてあるけどSS材じゃない!?」
と現場で工事監理者さんに言われた瞬間に心の中で
「マジー!!終わってるやん!」
と思わず叫んでしまいそうなシチュエーションですね。
まあ、現実的には鉄骨業者さんもプロなので、そんな場面は
あなたは遭遇する確率はかなり低いですが、0では無いですから。
というわけで、今回は鋼材の種類についてお伝えしていきます。
まず
タイトルにあるように鋼材の種類はいくつかあり、それぞれに
特徴があるため適材適所で使用部材を構造設計者さんが選定します。
例えば
SM材は部材同士を溶接でつなぐような場合に適しています。
なので、溶接で主に組立ていくような箇所にはSM材が
使用されている事が多いので、改めてそのような視点で
構造図の部材リストを確認してみてください。
続いて
SN材は、建築構造用圧延鋼材の意味であり
建築物の主要構造部に用いられる鋼材として、
SS材、 SM材の JIS 規格値を満足するだけでなく、
次のような条件も満足するような使用です。
- 降伏点の上限値規定
- 降伏比 (降伏点 / 引張強さ) の上限値規定
- 板厚方向の絞り値の下限値規定 (C材のみ)
- 化学成分のうち、より厳しい P、S 値の規定
- 炭素当量又は溶接割れ感受性組成の規定
- JIS G 0901 による超音波探傷試験による内部品質の保証 (C材では規格として義務付けられている。また、 B 材でもオプションで超音波探傷試験による内部品質の保証も可能である。)
だから
SS材やSM材よりも規定が厳しいため建物の主要構造部に
対して用いられる事が多いと覚えておきましょう。
特に柱のダイアフラム(後日解説します)などの板厚方向に
大きな力が作用する場合はSN材のC種を使う事が多いので、
理由を理解した上で、図面上でも特に気にして確認しておいた方が
よいと私は考えてます。
それから
SM材やSN材の性能が必要ない箇所は一般的にSS材が使われます。
使用部材がSS400だと最も一般的で何の変哲もない部材だと
思ってもらって結構ですよ。
最後に
「建築工事監理指針(令和7年版上巻)」の該当部分を確認して下さい。
P.515
(キ) 主な鋼材の種類
(a) 建築基準法に基づく告示に規定された主な鋼材の種類とその概要を表 7.2.3に示す。
なお、JIS G 3106 (溶接構造用圧延鋼材) で熱処理を行ったときは、記号の末尾に焼ならし N、焼入れ焼戻し Q、熱加工制御 TMC の各記号を付記することになっている。
また、JIS G 3106 で内部欠陥のないことを立証するために超音波探傷試験を行ったときは、記号の末尾に UT を付加して表す。超音波探傷試験は、JIS G 0901 (建築用鋼板及び平鋼の超音波探傷試験による等級分類及び判定基準)による。
なお、SN400C、SN490C は、出荷前に超音波探傷試験が実施されている。また、SN400B、SN490B は、オプションで超音波探傷試験ができることになっている。
JIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)に規定される SS400 材とJIS G 3106 に規定される SM490A材は、建築用鋼材として多く使用されているが、溶接性、衝撃特性及び板厚方向の性能が必要となる箇所に使用する場合は、特に、りん(P)と硫黄(S)の不純物の含有量に注意して使用する。
溶接性において、高温割れの主因は溶接金属のデンドライト境界面に残存する低融点の不純物にあるとされており、P や S 等が割れを促進する元素として知られている。また、T継手あるいは隅肉多層盛溶接部に発生するラメラテアは、圧延方向に伸長した鋼板の層状介在物(MnS)が原因のーつとされている。
さらに、この層状介在物(MnS)は、板厚方向の絞り値にも大きく影響する。参考として、各鋼種のP 及び S のJIS 規格値を表 7.2.4に示す。
なお、溶接接合の場合は、その部位の重要度に応じて P や S の少ないものを使用することが望ましい。
表7.2.3 主な鋼材の種類と概要 JIS番号 種類 代表的記号 概要 G 3101
(2015)一般構造用圧延鋼材 SS400
SS490
SS540橋、船舶、車両等の構造物に、最も一般的に使用される鋼材で、普通は SS材と呼ばれている。 G 3106
(2015)溶接構造用圧延鋼材 SM400A、B、C
SM490A、B、C
SM490YA、YB
SM520B、C橋、船舶、車両、タンク等の構造物に使用される溶接性の優れた鋼材。
Aは靭性値の規定がない。
B、Cの順に規定靭性値が高くなる。G 3114
(2016)溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材 SMA400AWW、BW、CW
SMA400AP、BP、CP
SMA490AWW、BW、CW
SMA490AP、BP、CP建築、橋等の屋外構造物に使用される溶接性と耐候性が優れた鋼材。
腐食の進行は、SS材の1/4以下。G 3136
(2012)建築構造用圧延鋼材 SN400A
SN400B
SN400C
SN490B
SN490CA種は二次部材に使用される。
B種は溶接性、塑性変形能力が保証されているもので、柱、大梁、筋かい等に用いられる。
C種はB種の性能のほかに、板厚方向に大きな引張力が作用する部位に使用される。G 3138
(2005)建築用構造用圧延棒鋼 SNR400A
SNR400B
SNR490B材質をSN材と同等とした棒鋼である。
構造用アンカーボルトやターンバックルボルトに用いられる。
A、B種の区分はSN材と同様である。G 3350
(2017)一般構造用軽量形鋼 SSC400 建築等の構造物に使用される冷間成形の軽量形鋼で、軽Z形鋼、軽山形鋼等がある。 G 3352
(2014)デッキプレート SDP1T
SDP1TG
SDP2T
SDP2G
SDP3建築、土木、車両等の構造物に使用される冷間成形のデッキプレート。
SDP1TG、SDP2Gは亜鉛めっきを施したものである。
SDP3は耐候性鋼。G 3353
(2011)一般構造用溶接軽量H形鋼 SWH400 土木、建築等の一般構造物に使用され、高周波溶接により成形される。
軽量形鋼、SS材と同程度の材質を持っている。G 3444
(2015)一般構造用炭素鋼鋼管 STK400
STK490土木、建築、鉄塔、足場、杭、支柱等の構造物に使用される炭素鋼鋼管。 G 3466
(2015)一般構造用角形鋼管 STKR400
STKR490土木、建築等の構造物に使用される角形鋼管。上記の鋼管(STK)と同程度の材質をもっている。 G 3475
(2014)建築構造用炭素鋼鋼管 STKN400W
STKN400B
STKN490B材質をSN材と同等とした円形鋼管である。
構造用部材として使用される。(注) 平成12年 建設省告示第1446号では、この表に掲げるもの以外にJIS G 5101(炭素鋼鋳鋼品)、JIS G 5102(溶接構造用鋳鋼品)、JIS G 5201(溶接構造用遠心力鋳鋼管)等が規定されている。
表7.2.4 各鋼種の P 及び S のJIS規格値 (単位 %) 鋼種 りん(P) 硫黄 (S) SS400 ≦0.050 ≦0.050 SM400A、B、C ≦0.035 ≦0.035 SM490A、B、C ≦0.035 ≦0.035 SM520B、C ≦0.035 ≦0.035 SN400A ≦0.050 ≦0.050 SN400B ≦0.030 ≦0.015 SN400C ≦0.020 ≦0.008 SN490B ≦0.030 ≦0.015 SN490C ≦0.020 ≦0.008
(ク) 建築構造用圧延鋼材 (SN材)
(a) 建築物の主要構造部に用いられる鋼材として、SS材、 SM材の JIS 規格値を満足するだけでなく、次のような条件も満足する。
① 降伏点の上限値規定
② 降伏比 (降伏点 / 引張強さ) の上限値規定
③ 板厚方向の絞り値の下限値規定 (C材のみ)
④ 化学成分のうち、より厳しい P、S 値の規定
⑤ 炭素当量又は溶接割れ感受性組成の規定
⑥ JIS G 0901 による超音波探傷試験による内部品質の保証 (C材では規格として義務付けられている。また、 B 材でもオプションで超音波探傷試験による内部品質の保証も可能である。)(b) JIS G 3136 の概要は、次のとおりである。
名称 :建築構造用圧延鋼材
鋼種種類の記号 :SN400A、B、C、SN490B、C
製造範囲 :板厚 6mm以上、100mm以下の鋼板、帯鋼、平鋼及び熱間圧延形鋼この鋼材の特徴は、次のとおりである。
① これまでの溶接性による識別のための鋼種記号 SS材、 SM材とは別に、建築用鋼材として鋼稜記号 SN材とする。
② 溶接性の保証の有無、板厚方向の引張り特性の保証等を、強度区分の末尾記号 A 、B、C で表示する。
A 主として弾性設計の範囲内で使用し、主要な溶接を行わない部材 (小梁、間柱、母屋、胴縁等の二次部材) に適用するもの。
B 溶接を行う部材であり、かつ、塑性変形能力を期待する部材 (柱、梁等耐震用主要構造部材 ) に適用するもの。
C 溶接性、塑性変形能力を必要としたうえで、さらに板厚方向引張応力が作用する部材 (溶接組立箱形断面柱のスキンプレート、通しダイアフラム等) に適用するもの。このため、 C 材では板厚方向引張り性能として絞り試験及び鋼板では UT (超音波探傷) 試験が実施される。
③ 引張強さの区分は、これまでの 400N と490N と同じ 2種類とする。それぞれに対する F値はこれまでと同じ扱いである。
つまり
鉄骨工事で資料されるSS材、SM材、SN材の特徴は
SS材は「一般構造用圧延鋼材」と呼ばれて建築現場で最も
一般的に使用されている鋼材です。
また、建築物以外にも橋、船舶、車両等にも使用されています。
SM材は「溶接構造用圧延鋼材」と呼ばれて溶接性の優れた鋼材で
SS材に次いで使用されている部材です。
また、建築物以外にも橋、船舶、車両、タンク等の溶接性が
重要な部分に使用されています。
SN材は「建築構造用圧延鋼材」と呼ばれて建築物用に開発された
鋼材でA~C種に分かれており、それぞれ下記の特徴があります。
A種は二次部材に使用されます。
B種は溶接性、塑性変形能力が保証されているもので、柱、大梁、筋かい等に用いられます。
C種は通しダイアフラム等の溶接性、塑性変形能力を必要としたうえで、さらに板厚方向引張応力が作用する部材に用いられます。
では
同じ鉄でも鉄筋の場合はどの様な材料種別なのでしょうか?
すんなり答えが出てこないあなたはこちらの記事を読んで
知識として入れておくことをオススメしますよ。
↓ ↓ ↓



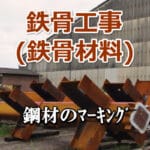




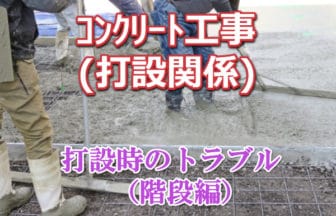




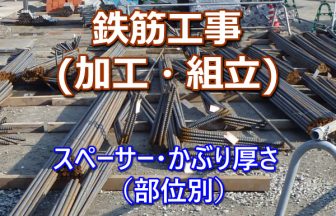

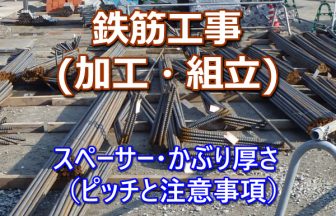
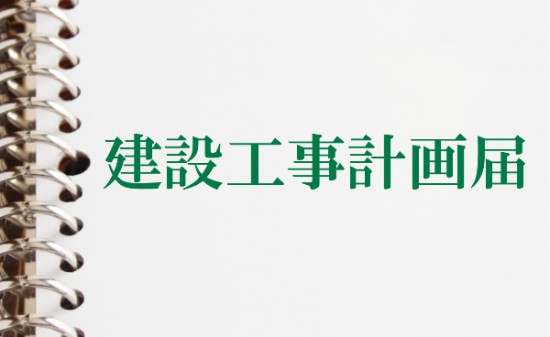






































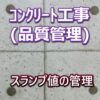
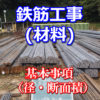





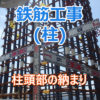
この記事へのコメントはありません。