「この部材の切れ端使いたいんだけどSS400?SM490?」
と聞かれてあなたは答えることが出来ますか?
実際の鉄骨材に何の目印も無ければ見た目だけで鉄骨材を
判別できる人はまずいないでしょう。
なぜなら
強度などが違ったとしても所詮同じ「鉄」だからです。
溶融亜鉛メッキであれば、普通の鉄と違うから見分けられる
とあなたは考えたかもしれませんが、メッキに漬けるのは
材料を完成形まで組み立てた状態で行うことが一般的です。
だから、組立時点ではどれも同じような茶色の鉄なのです。
では
実際には、鋼材の種類をどの様に判断しているでしょう?
鉄骨材は一般的に数m~十数m程度で工場で製作されます。
そこで、どの会社がどの規格の材料を製作したか?を
材料自体にマーキングしていきます。
だから
鉄骨材を眺めているとどこかに規格がわかるマーキングを
見つけることが出来るはずです。
長い材料なら…。
もし
鉄骨材に3mピッチでマーキングがしてあった場合では、
1mの切断した材料の場合にどこにもマーキングが
見当たらないという状況もおきる可能性があります。
だから
マーキングを行うピッチも350mm程度と規定されています。
では
「200mmに切断した場合はどうするの?」
とあなたは感じたかもしれませんね。
その場合は、切断したタイミングでそれぞれ何の規格が
手書き等でマーキングしています。
そうしないと
明日の自分は覚えていないかもしれないし、
次工程で溶接する時に別の人が作業したら確実に
分からないでしょうからね。
いずれにしても
大切なことはその場で判別できるように都度整理しておく。
という事です。あなたの身の回りに
「えっ、これ何の為に買ったっけ?」
というもの溢れていませんか(笑)?
最後に
「建築工事監理指針(令和7年版上巻)」の該当部分を確認して下さい。
P.518
(ケ) 鋼材のマーキング
建築構造用圧延鋼材 (SN材) には、切板に切断された段階でも明らかに規格材であると識別できるように、鋼板表面全面に社章あるいはドットマーク・規格名称をマーキングができることになっているので、マーキングのある材料を使用するとよい。
なお、形鋼には全面マーキングは行っていないが、全長にわたって連続マーキングしているものがある。マーキングの内容は、次のとおりである
① マーク表示面 :表 (おもて) 面全面
② マーク表示項目 :社章又は規格分別マーク又はドットマーク
1) SN400B、C 社章と菱形
2) SN490B、C 社章と円形
3) その他 社章
③ マーク表示ピッチ:長手、幅方向と もに 350mmピッチ程度
④ マーク寸法 :80mm X 80mm程度
つまり
鉄骨の加工用に切断した材料の品質はどの様に判別するのか?
については、それぞれの材料がどんな品質なのかを識別するために
マーキングを行って管理しています。
鉄骨部材というのはH型鋼などの部材だけでは製作できなくて、
鋼板なども組み合わせたり、柱に取付く梁部材など短く切断されて
製作されるものも意外に多いのが現実なのです。
実際には
あなたが1つ1つの材料について正しい材料か判断することは
無いかもしれませんが知識として知っておくことは大切です。
更に
鋼材にもいろいろな種類があり、強度も異なっています。
でも「何が違えば鋼材の強度が変わるのか?」について
あなたは答えることが出来ますか?
答えに詰まったあなたにこちらの記事がオススメですよ。
↓ ↓ ↓


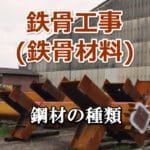









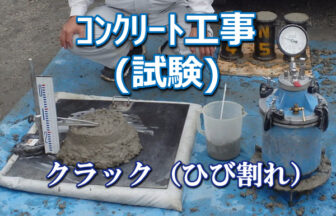
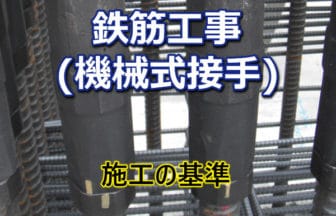
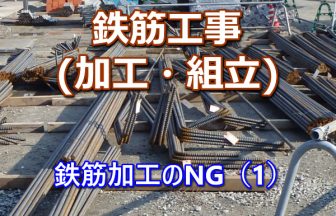

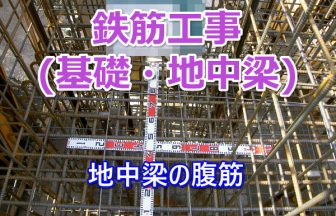









































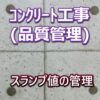


この記事へのコメントはありません。