鉄筋コンクリート造や鉄骨造の基礎などの建物で
特記仕様書に「ガス圧接」と記載されていたら当然、
鉄筋の継手はガス圧接すればよい。と感じるでしょう。
しかし
本当に何も考えずに「ガス圧接」しても良いのでしょうか?
実はこのパターンはガス圧接がNGという事は無いのでしょうか?
今回は
ガス圧接が可能な場合と、原則としてNGな場合についてお伝えします。
まずは、圧接が出来ない場合についてまとめてあるので、
「建築工事監理指針(令和7年版上巻)」
の該当部分を確認して下さい。
P.327
(2) 原則として圧接をしない場合
「標仕」では、SD345と SD390の鉄筋間を除き鉄筋の種類が異なる場合叉は径の差が7mmを 超える場合は圧接をしないとしている。また、令和 4年版「標仕」では、形状が著しく異なる場合として竹節鉄筋とねじ節鉄筋の圧接も行わないものとしていた。これについて、(会社)日本鉄筋継手協会「鉄筋継手工事標準仕様書 ガス圧接継手工事 (2017年・2024年補訂)」 は、同「ねじ節鉄筋のガス圧接継手性能に関する研究」においてこれらの圧接の性能確認を行った結果を踏まえて、節形状
によらず圧接できるとしており、施工実態の増加も鑑みて令和 7年版「標仕」でこれが認められることとなった。
なお、径の差について、平成31年版「標仕」までは径の差が5皿 を超える場合は圧接をしないとしていた。これは、径の差が大きい場合に鉄筋の熱容量の差によって相互の温度上昇に差異が生じて圧接不良が生じることを避けるための規定であったが、バーナー性能が向上したことゃ鉄筋冷間直角切断機による端面処理が一般的となったこと、(公社)日 本鉄筋継手協会「手動ガス圧接継手 径違い鉄筋圧接 (2サイズ違い :5mm を超えて7mm以下)の継手性能検証試験」で、全ての継手で細径側鉄筋の母材破断となり、降伏点及び引張強度が鉄筋母材の規格値以上であることが検証されたことを踏まえて、令和 4年版「標仕」で径の差が 7mm までに拡大されている。
また、これに関連する場合のガス圧接について、(公社)日本鉄筋継手協会の資料では、次の(a)、 (b)が示されている。(a) 「鉄筋継手工事標準仕様書 ガス圧接継手工事 (2017年・2024年 補訂)」 ではJIS G 3112(鉄 筋コンクリー ト用棒鋼)に適合する範囲で強度区分が隣接する種類の鉄筋間の圧接は可能としており、「異種・異径鉄筋の圧接継手性能評価に関する調査研究」でその性能が検証されている。
(b) 製造所が異なる鉄筋のガス圧接については、「鉄筋継手工事標準仕様書 ガス圧接継手工事 (2017年・2024年補訂)」 で圧接可能 としているが、SD490についてはデータが少ないので十分な事前検討が必要としている。
以上の項目の中で基本的な理解は出来たと感じています。
では
先ほどの項目の中で現場でトラブルになりそうなのは何か?
と問われると、あなたは一体何だと感じるでしょうか。
異種、異径、ネジ鉄筋、高強度、製造所違いどれですかね?
実は
私は「ガス圧接会社の職人さんがしっかりしていればトラブルは起きない」
という、あなたにとって意外かも知れない答えを持っています。
なぜなら
2サイズ違いが原則ガス圧接できないとか、SD345とSD390はガス圧接OK
という基本的な内容については、あなたよりも圧倒的にガス圧接を
行っている回数の多い職人さんの方が知っているからです。
もしも
大梁と小梁の取合い部分でSD390のD29と、SD345のD22が
ガス圧接すべき納まりで並んでいれば、きっと職人さんが
「監督さん!!これ2サイズ違いだけど圧接して良いの?」
と確認してくれるでしょうからね。
ただ
これらの中で1つだけトラブルが起きそうなのを1つ挙げるとすれば
SD490のガス圧接については、過去に施工した経験のある職人さんなら
疑いもなく施工してしまう可能性があります。
しかし
事前に、施工計画書によって鉄筋種別ごとの継手の計画を記載して
工事監理者さんの承認を得ていれば、施工すること自体がトラブルに
なるという事は無いので、施工計画書の時点で確認しておきましょう。
事前の技量試験が必要という結論になれば、忘れずに実施しましょうね。
つまり
ガス圧接を行う上で特記仕様書によらずに施工可能な条件は
- SD345と SD390の鉄筋間を除き、圧接する鉄筋同士の径が7mm以下の場合は施工可能
- ネジ鉄筋と異形棒鋼の圧接は可能
- 製造所の異なる鉄筋に関しても施工可能
上記の条件以外は特記仕様書によるか?設計者に質疑で
確認すべき内容だと考えています。
また
SD490以上はデータが少ないので圧接を行う場合は
必ず事前に確認及び承認を得てから施工するようにしましょう。
更に
SD490については、こちらでも基本事項を抑えておいて
知識をより深いものにしておきましょうね。
↓ ↓ ↓









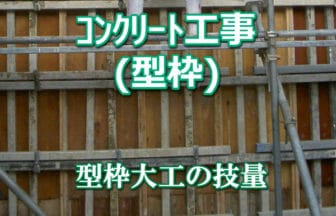


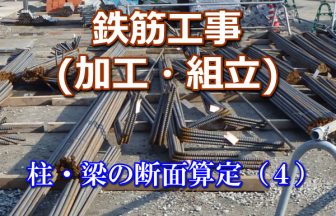
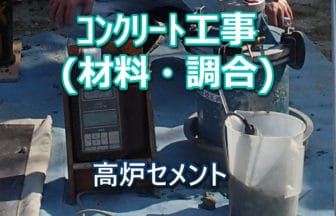

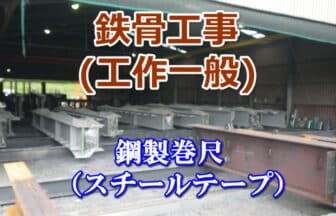





































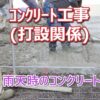


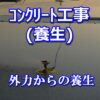






この記事へのコメントはありません。