型枠工事を進める上で、コンクリートの打設の回でも触れたが、
コンクリートを打設する土工さんとの情報共有をはかっておかないと、
打設後にジャンカなどのトラブルを抱える事になるので、
今回は壁の開口を中心にお伝えしていきましょう。
まず
開口の下の小口部分を型枠で塞ぐのか?空けたままにするのか?
具体的には
開口の幅がある程度広いと、開口の下部にフタされていると
コンクリートが中央までしっかりと充填出来ないリスクが高まります。
すると
「大工さん!フタ取って!!コンクリートが入らん!!」
とコンクリート土工さんから言われてバタバタしながら取ったと思ったら、
今度は
「あ~!コンクリートが止まらんわ~!大工さんフタしてよ!」
と逆に頼まれるパターンもあるので、どちらが良いか?
はケースバイケースですが、大抵の場合は、大工さんは「どちらでもOK」
なように型枠を加工している事が多いです。
次に
比較的大きな開口の場合は、型枠を建て込んだ後でも壁を挟んだ向こう側と
材料をやり取りする必要があったり、通路として使用したりするために
「開口」となっている事が多いです。
しかし
600mm四方の開口であれば、隣に大きな開口があれば、
先程のような必要はありませんし、型枠の加工の手間を考えると、
「普通に開口のない壁」として組み立てつつも開口部分だけ壁厚分の
枠を入れてコンクリートの堰(せき)を作る場合もあります。
すると
型枠を建て込んだ後は、「開口がある」という事を認識出来ません。
その場合はコンクリートを打設中に「何時迄たっても充填できない場所」
であったり、気付かずに打設後に「充填不良」を引き起こしたりします。
だから
寸法の小さな開口などがある場合は、コンクリート打設前に
あらかじめ「開口部」と分かるように明示しておくと良いですよ。
3つ目は
コンクリートの打設とは関係ないですが、開口部廻りには
サッシを取り付けるための「ダキ」などと呼ばれる欠込みがあり、
サッシの形状や廻りの仕上げの種類によって様々なパターンがあり、
その1つ1つを理解して型枠大工さんに明示しなければ行けません。
「まだ、仕上げの事なんて分からないよ~」
という気持ちにあなたがなっているかも知れませんが、
サッシ図とニラメッコしながら格闘する時間を、
是非とも作って頂きたいですね。
また
サッシに水切りがつく場合は開口部の下部が外部に向かって
斜めに下がっている納まりになるのですが、
数年後に外壁が劣化してきた時に「漏水防止」にもなるので、
必ず確認しておきましょうね。
最後に
「建築工事監理指針(令和7年版上巻)」の該当部分を確認して下さい。
P.439
(d) 窓及び階段は、図 6.8.13 のようにコンクリー卜が盛り上がるのを防ぐために端部にふたをする。窓の場合は、外側へ勾配を付ける。また、小さい窓等の下枠は全閉とし、空気穴を設けてコンクリートの充填具合を点検する。
図 6.8.13 窓及び階段のふたの例
つまり
型枠工事で壁開口の組立で事前に確認すべき3つのポイントとは、
- 壁開口の下端の型枠で「フタ」をするのか?
- 小さい寸法の開口は片面を壁で潰すのか?
- 水切り勾配や欠込み(ヌスミ)は適切に入っているか?
特に
はじめの2つの項目に対しては、コンクリート打設前に
よく型枠大工さんと打合せした内容を、土工さんに伝えないと、
コンクリート打設当日になって様々なトラブルに
見舞われてしまうので注意して下さいね。
こちらの記事ではコンクリート打設の立場から
書いているので合わせて読んでみて下さいね。
↓ ↓ ↓
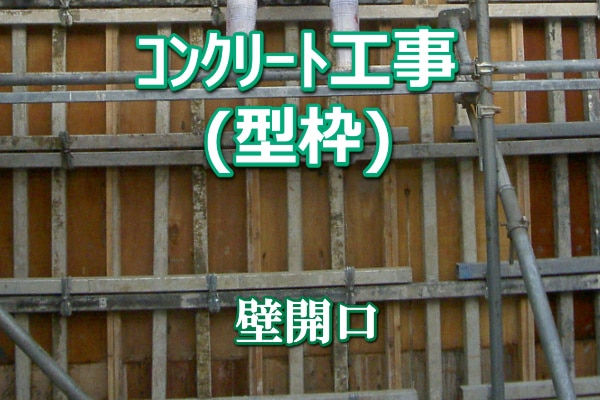
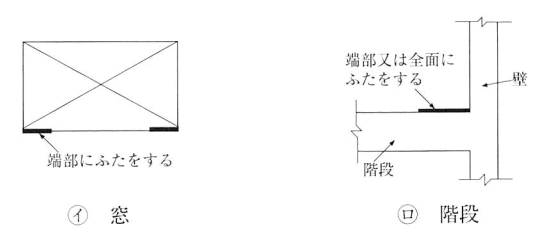


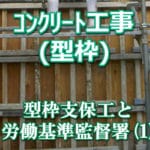





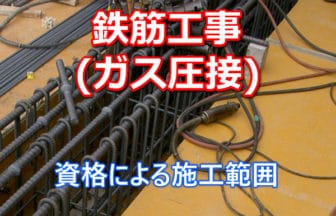
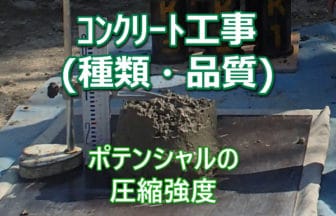

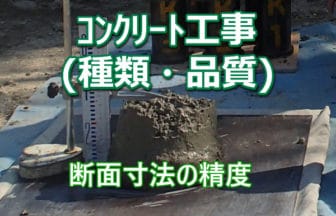
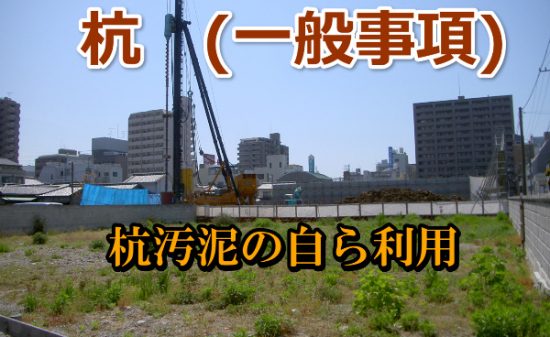
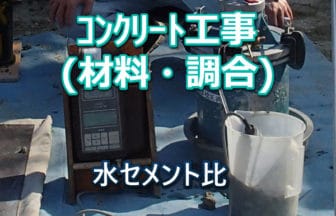
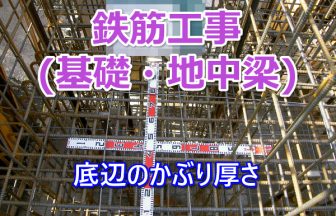










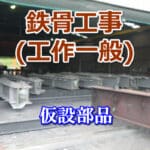


























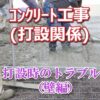




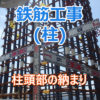




この記事へのコメントはありません。