天井インサートとは、仕上げ時にコンクリートスラブから重量物や
天井の軽量鉄骨下地を吊る時に用いられる受け材です。
|
|
天井インサートはスラブの型枠に大工さんがハンマーで打ち付けるだけ
という手軽な方法で設置する事が出来るので、コンクリート打設後に
後施工アンカーを打設するよりもコスト面でも労力面でもメリットかあります。
そして
天井インサートの配置図については、型枠大工さんへ渡すのに
私自身がよく書いていましたので、今回はその経験を生かして
「失敗しない天井インサート図の書き方」をお伝えしていきましょう。
まず
図面上綺麗だからと言って中途半端な寸法で等分割するはやめましょう。
具体的には
天井インサートは軽量鉄骨下地用であれば、壁面から150mm以内、
内部は900mm以内に配置しなければ行けませんが、3350mmを
割り込むのに4分割して837mmピッチにする事はやめた方が良いです。
なぜなら
現地では837mmで墨出しするのは非常に手間だし必要性がありません。
それよりは900mmをベースに割り込んで、残りを中途半端に出した方が
墨出しの時に桟木などに900mmの印をあらかじめ付けておいて、
スラブに置いて印を付ける方が圧倒的に効率的だからです。
次に
部屋の中心、廊下の中心などは設備のインサートと干渉する可能性が
高いので敢えてずらして記入する事が大切です。
ちなみに
先程の項目で、中途半端な寸法で等分割しないようにというのは、
実は今回の項目にも当てはまっていて、敢えて等分割していないのです。
なぜなら
電気の照明の位置は意匠上部屋や廊下のセンターに無いとおかしいですし、
ダクトのルート等は入口と出口が決まっているので必然的にルートは決まります。
しかし
天井のインサートは900mm以内であれば良いので、壁際で無ければ
設備系のインサート位置をずらした方が、後から
「監督さん廊下中央のインサート、照明と干渉して全滅だよ!」
と軽天屋さんに言われなくても済みますからね。
逆に、設備には壁から150mmの位置にはインサートを設置しない
ように伝えておけば後施工アンカーの本数も減りますよね。
3つ目は
オプションや設計変更などの可能性のある場所には、天井を造るなら
あらかじめ天井インサートを仕込んでおくと良いです。
なぜなら
天井を左官さんで補修して直にクロスなどを張る仕上げは別として、
天井下地を組む場合は、数個余分に天井インサートが設置されていても
全く問題にならないですし、型枠大工さんも数個打ち付ける数が増えても
95%以上の確率で文句を言わないからです。
だから
可能性のある箇所については天井インサートを計画しておきましょう。
最後に
天井インサートは暗黙の了解的に色分けが決まっています。
私の経験上多いのが建築は黄色、電気は赤色、設備は青色、
ガス工事など設備で会社が違え緑色という分け方が多いです。
だから
「俺は赤色が好きだから!」
と勝手に注文すると後でトラブルになる可能性は大きいですから
事前に関係業者で打合せておきましょうね。
つまり
天井インサート図の割付時にTMが経験上気を付けている事とは、
- 図面上綺麗だからと言って中途半端な寸法で割り込まず、900mmをベースに割り込む
- 部屋の中心、廊下の中心などは設備のインサートと干渉する可能性が高いので敢えてずらして記入する
- オプションや設計変更などの可能性のある場所にはあらかじめ仕込んでおく
また
現場で施工する前に、建築・電気・機械・ガスなどで天井インサートの
使用する「色」について打合せしておく事が大切だと考えています。
特に
図面上綺麗に納めたいという気持ちと、現場で後からやり直す手間を
可能な限り防ぎたいという気持ちは「それぞれが正解」だと感じます。
そこで
大切なのはこちらの記事の内容だと感じますので、
合わせて読んで無用なトラブルは防いで下さいね。
↓ ↓ ↓
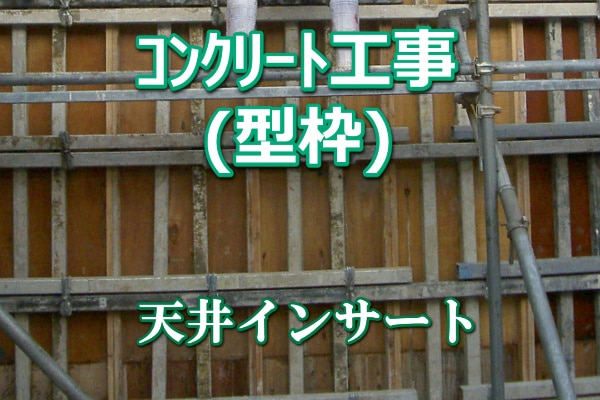









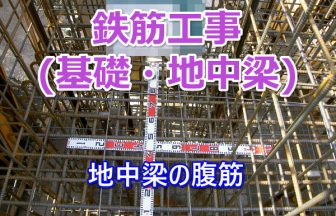

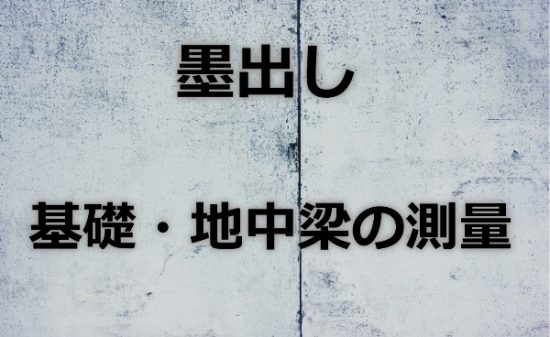



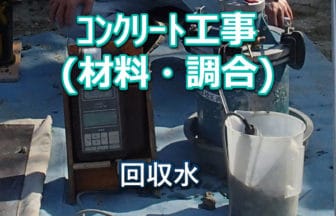
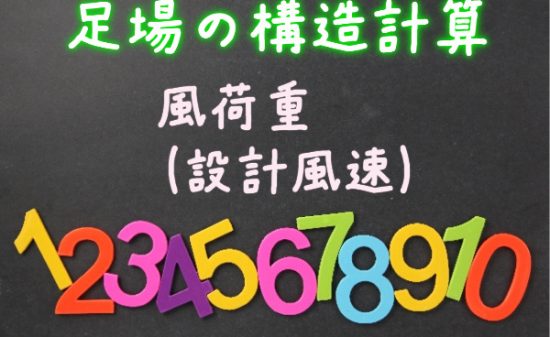
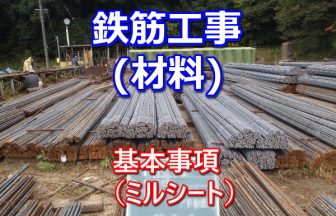









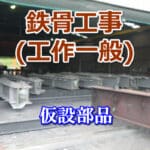




























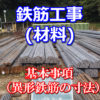
均等割にするか、900割にして最後を2分するか、900で割り切るかで悩んでました。「部屋の中心になりがちという理由で均等割はダメ、大工さんの効率てきには割り切りがいい」というのは、なるほどなと勉強になりました。柱型付近の野縁受の煩雑さを避けたいので野縁受方向は柱型スタートでいきますが、それ以外は基本割り切ることにします。ありがとうございました!