鉄筋の強度について以前お伝えしたことがあるが、
その時に例外としてあげたのが今回お伝えする予定の
「高強度せん断補強筋」である。
高強度せん断補強筋というのは、現在では特別な材料ではなく、
きっと10階建て以上の鉄筋コンクリート造の建物なら
普通に用いられているのでは?と感じるくらいの材料である。
ちなみに
高強度せん断補強筋については「建築工事監理指針(令和7年版上巻)」
にて簡単に解説されているので紹介しておこう。
P.307
(7) 近年では、せん断補強として、高強度せん断補強筋が用いられることがある。これは、降伏点が685N/mm2、 785N/mm2等の材料であり、せん断補強筋量を低減させることができる。また、梁貫通の補強筋としても、鉄筋径を低減させることができることから、使用されている。最近では、許容応力度 1,275N/mm2の材料 も用いられることがある。ただし、これらは大臣認定品であり、せん断耐力の強度式とリンクしていることや折曲げ寸法についても注意が必要である。
これで
高強度せん断補強筋の簡単な説明は終わりにして本題に入るが、
高強度せん断補強筋というのは、文字通り「高強度」である。
となると、何か不具合があったからといって「現場で加工」
するのは極めて難しい材料なのだ。
だから
高強度せん断補強筋は「工場加工」されてくるので、
発注寸法などを間違えると、再発注すべき材料であり
現場で何とかしようとしても鉄筋屋さんに断られることに
きっとなるだろうと感じるよ。
そして
高強度せん断補強筋を梁に使用する場合は「フックの折り曲げ寸法」
に注意することが必要だね。
なぜなら
特記仕様書には「6d」と記入されている曲げ寸法が
高強度せん断補強筋であれば「8d」と大きくなっている
場合があるからだ。
すると
梁の主筋が2段筋になっている場合に、高強度せん断補強筋と
主筋が「干渉」してしまう可能性が高いからである。
もしも
鉄筋の納まり上で、干渉しない場合でも知識として覚えておいた方が
良いと私は感じる。
特記仕様書の記載内容次第だけど、結果的に異なる内容になる場合は
質疑書とカタログを添えて承認を取っておくことが大切だからね。
つまり
高強度せん断補強筋について知っておくべき2つのこととは
- 強度が高くかつフープなどは溶接接合を行っているので現地加工が出来ない。
- 端部のフックの長さが通常の鉄筋より長い場合が有る。
ということである。
建築現場に限らず工場製作物は、加工寸法などを間違えると
「一円の価値もない商品」にいっきになリ下がってしまう。
だから
事前に失敗しないように十分注意して検討できれば良いけど
なかなか思うようにはならないというのが現実だよね。
現場を巡視したりする場合でもきっと同じだと私は感じるよ。
だから、こちらの記事も合わせて読むことをオススメしておくね。
↓ ↓ ↓
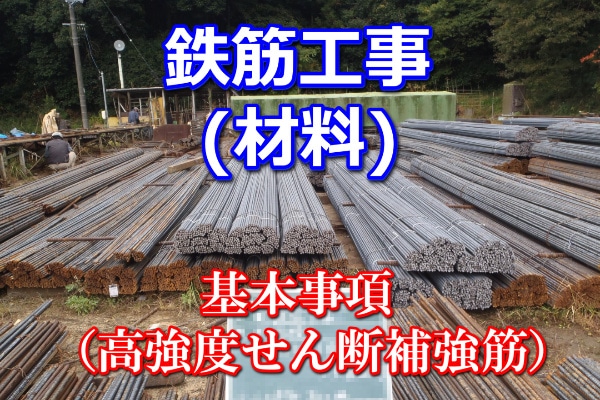







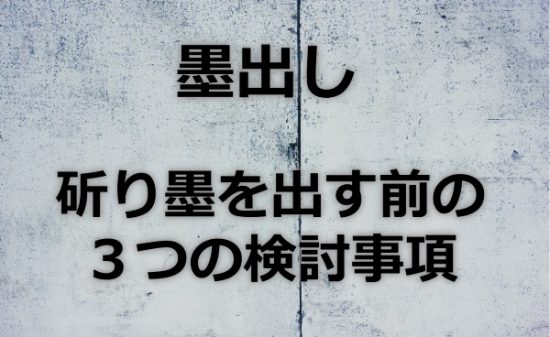



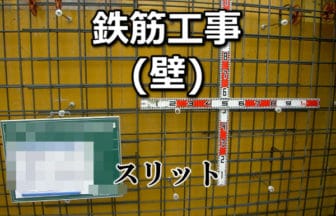

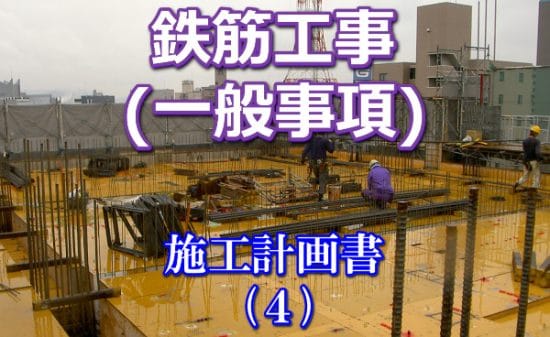

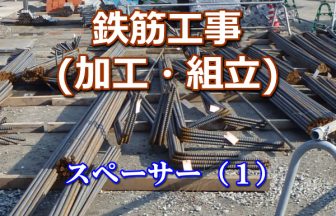






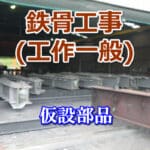
































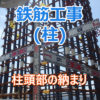
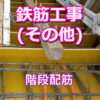



この記事へのコメントはありません。