前回の記事で自立式山留め工法の場合は、変位の管理が重要であると書いた。
では
山留めの変位の管理を怠ると、最悪どのような事態が待っているのか?
はじめに結論から述べると「山留めの崩壊」である。
もしも
山留めの崩壊が起こってしまったらとても大変な事態になるのは
想像に固くないよね。
山留めを設置する場合は、近接して道路や家屋があることも多く、
山留めの崩壊によってかなりの影響を受けてしまう。
もしかしたら、道路の決壊や家屋の倒壊までなるだろう。
実際に
私は自分で山留めの崩壊を経験したことは無いけれど、
写真で崩壊現場を見たことがある。
「うぁ~!これってどうやって復旧するんだろう?」
というくらい凄まじい状況であった記憶があるよ。
そのくらい、山留めの崩壊って自分では絶対に起こしたくない事故。
でも
事前に山留めの構造計算しているから安心なんじゃ無いの?
とあなたは感じるかも知れないね。
でも、構造計算通りになるのは見えない地層が想定通りで、
かつ想定通りの挙動を示した場合のみ。
特に、軟弱地盤であれば一定の変位を越えると、
一気に変形が進んで取り返しのつかない状態になることもある。
このように、予想以上の変形が出たことは私も経験しているので、
地中の工事は思い通りにいかないものである。
と思い知らされた。
だから
この記事を読んでいるあなただけには悲惨な事故を
経験して欲しくないので、山留めの変位の管理をしっかりしてね。
つまり
自立式山留め工法において変位の管理が最重要である理由は、
変位が急激に増えると最悪は山留めの「崩壊」という事態を招くから。
一旦山留めが変形して崩壊すると、周辺の道路や家屋にも
多大な悪影響を与える大惨事になってしまう。
だから
日頃から「変化していない」ということを確認するように心がけようね。
継続的に計測をしておけば、突然の異変には絶対に気づけるからね。
このようになってしまってからでは遅いからね。
↓ ↓ ↓








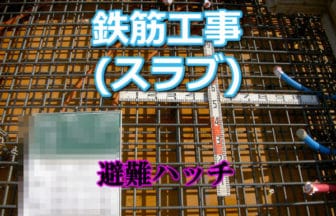


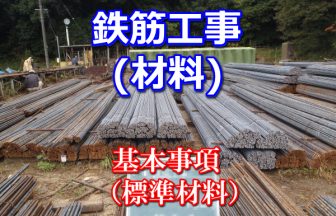

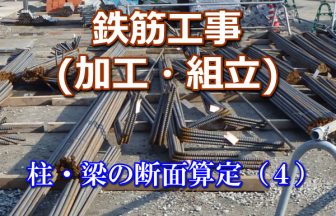
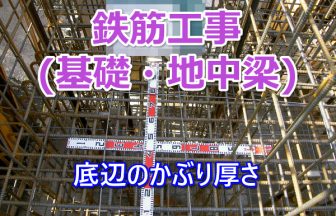
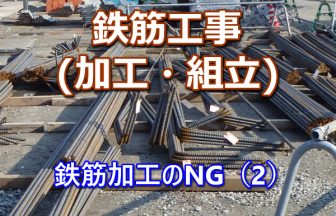




































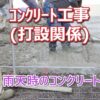



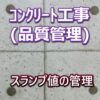






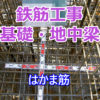
日頃から「変化していない」ということを確認するように心がけようね。
その通りですね(^o^)