鉄筋を現場で組み立てるには所定の形状に加工する必要がある。
そこで、「加工」とはどのような作業か?というと、
「切断」と「曲げ」である。
具体的には
鉄筋を所定の長さに「切断」をしてから、所定の位置で「曲げ」る
ことによって、9割の鉄筋の加工は完了する。
それだけ、複雑に組み上がる鉄筋の形状も1つ1つは複雑ではない。
ここで
「建築工事監理指針(令和7年版上巻)」を事前に確認しておこう。
P.310
(2) 熱間圧延鉄筋でも白熱化して空気中で冷却すると鉄筋の性質が変わるので、曲げ加工の場合でも、原則として、常温で加工することとしている。
(3) )冷えている鉄筋に点付け溶接を行うと、急熱、急冷されるので焼入れ (7.2.1(2)(オ)参照)を行ったことになることから、熱影響部(7.6.7(9)(イ)参照)が著しく硬化し、鉄筋がもろくなり、この部分を少し曲げただけでひび割れが発生する場合があるので、「標仕」ではこれを禁止している。また、鉄筋にアークストライクを起こすと断面欠損が生じたり、局部的な急熱、急冷による悪影響があるので、「標仕」では
これを起こしてはならないとしている。
なお、溶接金網等で鉄筋の交点を電気抵抗溶接としたものは、点付け溶接とは見なさない。
つまり
鉄筋を熱してはイケないという理由は「性質が変わるから」。
性質が変わると当然ながら所定の強度が出ない可能性がある。
そして
所定の強度が出ている鉄筋か?どうかなんて現場では分からない。
少し脱線するけど、現場においてコンクリートの打設後の台直しなどで
「ガスであぶって曲げてしまえば良いじゃない」
という、目先の楽しか考えていない作業員さんは言うかもしれない。
当然、斫り込んだりすることは手間も時間もお金も掛かる。
まして、コンクリート打設後の現場なんかは「戦争状態」のように
さまざまな作業員さんたちが慌ただしく働いている。
「別にバレなければ良いか」
と、悪魔のささやきに耳を傾けてしまいたくなることも有るだろう。
でもね
良いも悪いも色々経験してきた私があなたに言いたいことは
「隠しても案外バレれしまうことが多い」という事と、
「バレた後の後処理のほうが100倍大変」という事。
例えば
先程の現場で無理な台直しをしたケースで行くと、
- 台直しを行った後の状態を発見される
- 誰かから密告される
- 地震などの挙動時に判明
の3つがパッと頭に思い浮かんだ内容だね。
まず
不自然は補修方法というのは、ある一定のレベルの人から見ると
「非常に不自然に映る」ことが多いのが現実である。
何気なく現場を歩いていても「あれっ」と一瞬目がとまる事がある。
そこには、大抵何かしらのトラブルが有ることが本当に多いよ。
そして
現在のネット社会では、どこで誰が「真実」をアップしているか
本当にわからないよね。普段は良好な関係を築いていたとしても
何かトラブルが発生して「暴露」というケースも実際にあるからね。
更に
竣工後に実際に地震が発生した時に、不具合が発生して
慌てふためく姿を、あなたは想像できるかな?
技術者としては一番避けて通りたい内容だね。
今回は少し脱線が長すぎたので、
次回は鉄筋の溶接についてお伝えしていこう。
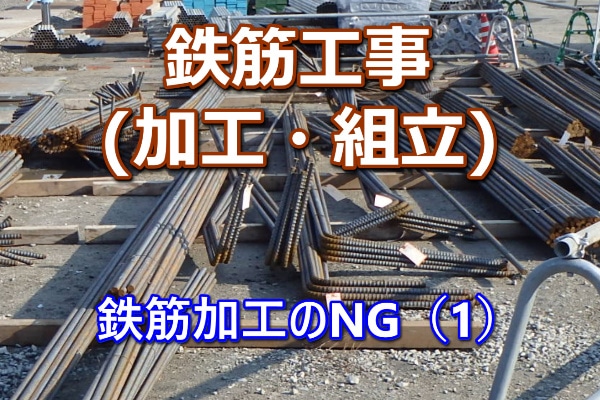






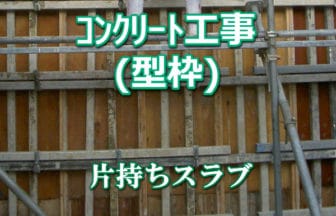
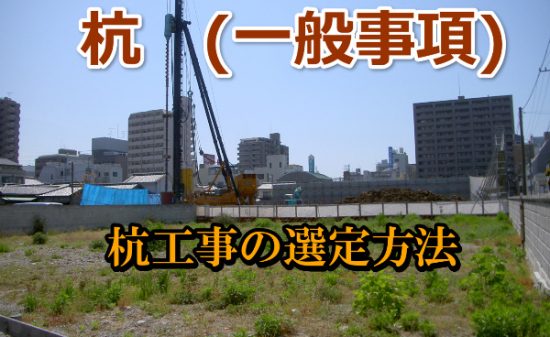
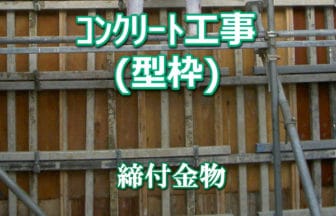


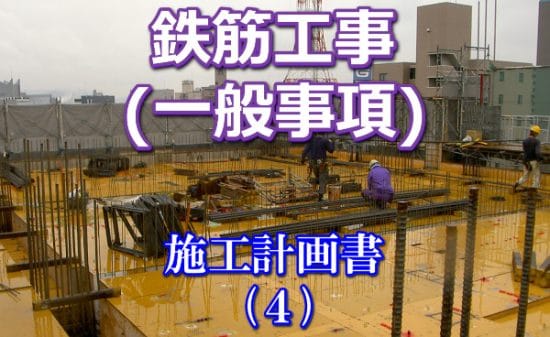
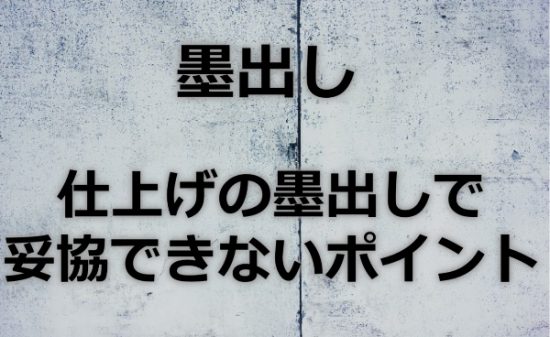

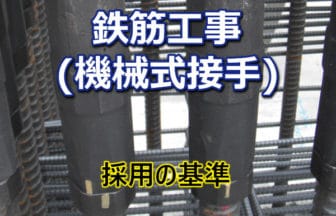






































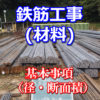

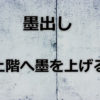



この記事へのコメントはありません。